
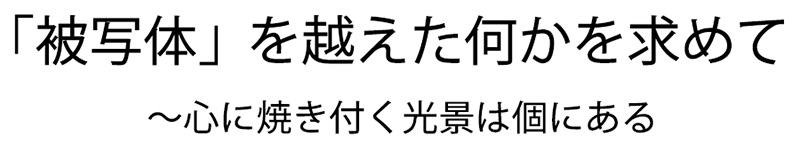

 ISに一時拘束されたことがあるヤズディ教徒の女性。ISに姿を確認されないよう、ヤズディ女性が頭を覆う伝統的な白いスカーフ越しに撮影した。同じ境遇にあるヤズディの女性たちが他にも数多くいる。目を凝らして表情を見てもらい、その存在を感じてもらいたかった。
ISに一時拘束されたことがあるヤズディ教徒の女性。ISに姿を確認されないよう、ヤズディ女性が頭を覆う伝統的な白いスカーフ越しに撮影した。同じ境遇にあるヤズディの女性たちが他にも数多くいる。目を凝らして表情を見てもらい、その存在を感じてもらいたかった。
©林典子
今回の「表現者たち」は、ドキュメンタリー写真家の林典子さんです。
林さんの代表作は、ジェンダーや社会と個人の記憶に焦点をあてた、長期的な密着取材を進める中で、その多くが生まれています。
時間をかけて情報を集め、現場では取材される側との関係を深めながらストーリーを構築し記録。写真集や月刊誌、著作本等で発表されています。
硫酸に焼かれた女性たち(2010年、パキスタン)や、キルギスの誘拐結婚(2012年)では、日本に暮らす者には理解しがたい複雑な慣習や不条理をルポ。
2015年から2017年にかけては、少数民族ヤズディの村シンガルなどで、中東に勢力を広げたイスラム過激派組織「イスラム国」(IS、現地の呼称でDaesh=ダーシュ=)によって日常を奪われた人々の記憶に向き合い、望郷の想いを抱えながらも、生き抜く姿を記録しました。ダーシュの戦闘員に捕まった女性たちの多くは、親族を殺害された上に、性的暴力も受けるなど生涯癒えることのない心理的、身体的な傷を負いました。
北朝鮮に暮らす日本人妻の取材では、岩波新書から2019年に、『フォト・ドキュメンタリー 朝鮮に渡った「日本人妻」–60年の記憶』として出版され、今も取材を続けられています。
20世紀以降の戦争やテロ、内紛などによる心の傷は、21世紀に入っても簡単には癒えません。個の人々の声や表情を足で拾い集め記録、写真と文で発表してきた林さんのドキュメンタリー作品は、個の人格の貴重な痕跡として過去と今をつないで、我々の心に迫ってきます。
(企画・構成 秋山哲也、協力・石井真弓、中村惠美)
ドキュメンタリーフォトグラファーを目指すまで
大学在学中の2006年から07年にかけて、西アフリカのセネガルとガンビアを研修で訪れましたね。 その時のお話しを聞かせてください。
メディアの窮状を知る
たまたまアメリカの大学で西アフリカへの研修に参加する学生を募集する貼り紙を見つけ、2006年夏に15名ほどの学生と教授とでガンビアを訪れる機会がありました。当時ガンビアは独裁政権で、言論の自由・報道の自由というものがありませんでした。研修中のある日、人権問題に関するアフリカ連合の会議を傍聴し、ガンビア人ジャーナリストがメディアの窮状を訴える場面を目撃したのです。
地元新聞社での実地研修で学んだ「伝える意義」
同国のことをより深く知ろうと、私は3週間の研修後1人で現地に残り、地元の新聞社を訪れました。運よく、記者たちの取材活動に同行させてもらい、撮影した写真は新聞にも掲載されました。
記者たちは権力側の脅迫にもひるまず、自由に発信しようともがき苦しんでいました。ガンビアではメディアのあり方を間近に感じ、伝えることの意義を考える貴重な機会を得ることができました。
 大学の研修で訪れたセネガルで。湖畔を移動する羊飼いの少年(2006年7月)©林典子
大学の研修で訪れたセネガルで。湖畔を移動する羊飼いの少年(2006年7月)©林典子
2007年6月にはガンビアを出て、以前から関心をもたれていたというリベリア共和国も訪れていますね。当時の忘れられない状況や、衝撃を受けた出来事などを聞かせてください。
リベリアにはガンビア滞在後に約2週間滞在しただけですが、当時は内戦からわずか数年後ということもあり、国中が荒廃していました。戦争で家族や家、仕事全てをなくしてしまった方たちや、隣国のギニアやシエラレオネに逃れていたリベリア人の避難民が帰還をしている状況も目の当たりにしました。
当時の私はガンビアでのちょっとした経験があるくらいで、特に写真家としての自覚もありませんでした。しかし、現地で出会ったNGO関係者やジャーナリストに助けられながら、こうした不安定な社会で行動する上で必要なことや、その状況下に生きる人々と関わる上で大切なことを学んだと思います。
大学では国際政治学と紛争論を専攻され、国際機関での援助の仕事に就く道も考えられたということですが、フリーランスのフォトグラファー&ライターとして歩む道を決めたのはこのころからですか?
はい。ガンビアでの経験を通して、メディアや写真に関わる仕事をしたいと思うようになりました。
心に焼き付いた光景
2011年、16年、19年にはカンボジアで、母子感染によるHIV患者ボンヘイさん(当時8歳)を継続取材されていますね。被写体の生きざまを、共に生活をしながら取材するスタイルのさきがけだったと思います。
耳も聞こえず、言葉が話せず、HIV/エイズの存在自体も知らずに、HIV感染と知らずに生活していたこの少年や家族への取材を通じ、一番心に残る思い出などをお話しください。
HIV感染と知らずに生活
「一番心に残る」思い出を絞るのは大変ですが、初めてボンヘイに出会った時(当時8歳)にはHIVに感染しているという重い現実に向き合いながらも、母と祖母に支えられながら、生きていました。2回目(2011年)に再会した時には、すでにエイズを発症していた母を亡くしており、ボンヘイ自身が祖母を支えなくてはという覚悟を持っていた印象を受けました。
生活を続けていくために、遊園地に行っては、そこらじゅうに落ちている空き缶を祖母と拾ってお金に換えて暮らしていました。同世代の子供たちが家族と遊園地の乗り物などに乗って楽しそうに遊んでいる横で、黙々と缶を探して集めているボンヘイの姿が心に焼き付いています。
 意思疎通ができずに祖母の腕の中で暴れるボンヘイ(2009年11月)©林典子
意思疎通ができずに祖母の腕の中で暴れるボンヘイ(2009年11月)©林典子
 ろう学校での授業中に集中力がなくなり席を離れて、教室の窓格子に毛糸を巻きつけて遊ぶボンヘイ(2009年11月)©林典子
ろう学校での授業中に集中力がなくなり席を離れて、教室の窓格子に毛糸を巻きつけて遊ぶボンヘイ(2009年11月)©林典子
 懐いている犬に頬を寄せて微笑むボンヘイ(2009年11月)©林典子
懐いている犬に頬を寄せて微笑むボンヘイ(2009年11月)©林典子
5年ぶりの再会、そして・・・
最後にボンヘイに会ったのは16年1月でした。5年ぶりの再会は道端でした。祖母も亡くなり、孤児となったボンヘイはNGOに引き取られて暮らしていたこともわかりました。彼がHIVに感染していることを以前から知っていたので、すぐに地元の病院に連れて行き、以前のようにケアを続けているのかを聞きに行った際に初めてそのことを知ったのです。
時々NGOの施設を抜け出して道端で寝泊まりをしながら、他のストリートチルドレンの子供たちと一緒に溜まっていることもありました。外国人旅行者たちがお金や食べ物を彼らに分け与えることもあったそうで、もらったものを他のストリートチルドレンに分け与えているところも見ました。
道端の片隅でボンヘイを見つけ私と目が合うと、いきなりカメラでシャッターを切る真似をして、私のほうを見てケラッと笑っていました。「写真を撮る人」と私のことを記憶していてくれていたのだと思い、素直に嬉しく思いました。ボンへイは、ろうあなので言葉を話すことも、聞くことも出来ないのですが、私とはジェスチャーで会話をしました。
その数ヶ月後にボンヘイはエイズを発症し、14歳で決して恵まれたとはいえない境遇のなか短い人生を閉じます。ボンヘイが危篤状態になった時、その数時間後に亡くなったこと、そしてささやかに営まれた彼の葬儀の様子などを、その都度現地のNGO職員の方が写真を送って報告をしてくれました。 彼と出会ってから最後に会った7年の間、逞しく生き抜いてきたボンヘイの姿を垣間見たこと全てが心に残っています。
ドキュメンタリーフォトグラファーとして
2015年から16年にかけてイラク北西部山岳部の少数民族ヤズディの取材をされています。当時はイスラム過激派組織「イスラム国」(IS)が勢力を拡大していた時期であり、安全の確保に気を使われたと思います。男性中心に動く社会構造で、生活習慣も大きく異なるイスラム教の国々での取材は、戸惑われた経験も多かったのではないでしょうか。
ヤズディの取材や、パキスタンの硫酸をかけられた女性被害者の取材(2010年)の様子や、そこで表現したかった点などについてお話しください。
 ISの攻撃から逃れ、シンガル山の村から難民キャンプに避難したヤズディのアドル。テントの周りでほうき草を育ててほうきを作っている(2016年7月)©林典子
ISの攻撃から逃れ、シンガル山の村から難民キャンプに避難したヤズディのアドル。テントの周りでほうき草を育ててほうきを作っている(2016年7月)©林典子
 アドルが暮らしていたシンガル山麓のドグレ村の生い茂った庭に取り残されたベッド(2016年7月)©林典子
アドルが暮らしていたシンガル山麓のドグレ村の生い茂った庭に取り残されたベッド(2016年7月)©林典子
人身売買や性暴力の被害者の声を記録
一口にイスラム圏と言っても、私はイラクやパキスタンなどでの取材経験があるだけです。現地で生活していると、日本では日常的には経験しないような不自由さや、ある程度の制限を強いられることはあります。現地で暮らしている女性たち一人一人はとても自立心があり、内面的にも強い人たちばかりです。家庭内での発言権を持っているのは実は女性が多かったりもします。
私がイラク北西部でヤズディの取材を始めたのは2015年2月です。現地ではまだISの脅威が続いていました。
ヤズディの人口は世界全体で約60万人から100万人と言われ、イラク、トルコ、シリア、アルメニアなどの地域に分散していますが、約30万人がイラク北西部のシンガル山や周辺の村々で暮らして来ました。彼らの信仰は口承で伝えられてきたため、その起源や歴史に関する正確な記録は残っていませんが、ゾロアスター教、イスラム教、キリスト教などに通じる部分があります。
2014年8月3日未明、ヤズディを邪悪な信仰だとする、イスラム過激派組織「イスラム国」(IS)が、シンガル山周辺に暮らすヤズディの村々を攻撃しました。その際、約5000人もの男性や高齢女性たちが殺害され、約6000人の若い女性たちは拉致され、戦闘員による人身売買と性暴力の被害に遭いました。
 ドイツへ避難した18歳のヤズディ男性ジョージがイラクから持参した時計。ヨーロッパへ向かう前に、高校時代の親友からプレゼントされた。イラクからヨーロッパへは陸路で密航斡旋業者を通して移動。そのため必需品以外は箱にしまった時計のみをリュックに入れて移動した。彼にとって時計は故郷の記憶を象徴するものとなった(2016年10月)©林典子
ドイツへ避難した18歳のヤズディ男性ジョージがイラクから持参した時計。ヨーロッパへ向かう前に、高校時代の親友からプレゼントされた。イラクからヨーロッパへは陸路で密航斡旋業者を通して移動。そのため必需品以外は箱にしまった時計のみをリュックに入れて移動した。彼にとって時計は故郷の記憶を象徴するものとなった(2016年10月)©林典子
心のよりどころに目を向け
2014年8月に私は別の取材のため、たまたまトルコに滞在していました。その時にISに村を攻撃されたヤズディの人々が国境を超えてトルコへ避難してきたのです。現地の報道を一緒に見ていたトルコ人の友人が、「ISも酷いが、ヤズディにも同情できないと」という言葉を発しました。普段は差別的なことを発することのない友人の言葉に驚きました。なぜヤズディが攻撃されたのか? ヤズディの人々についても知りたいと思い、2015年2月、イラクへ取材に向かいました。
現地でヤズディの家庭に泊まらせていただきながら、何が起きたのかを検証し、目の前の出来事を記録していく過程で、着実に新たな道を歩み始め出そうとしていたヤズディの人々が大切にしてきたモノ、思い出の写真、残された土地など、彼らの記憶をかき集めるようなやり方での取材に変化していきました。
 シリアやトルコなど国境を超えてイラクに入り、シンガル山の警戒にあたるクルド人女性兵士たち。3つの旗は、彼女たちが所属するPKK(クルディスタン労働者党)の軍事部門HPG (People’s Defense Forces) と、女性部隊YJA STAR(Free Women’s Units)、シンガル軍事部門YBŞ(The Sinjar Resistance Units) を表している (2015年3月) ©林典子
シリアやトルコなど国境を超えてイラクに入り、シンガル山の警戒にあたるクルド人女性兵士たち。3つの旗は、彼女たちが所属するPKK(クルディスタン労働者党)の軍事部門HPG (People’s Defense Forces) と、女性部隊YJA STAR(Free Women’s Units)、シンガル軍事部門YBŞ(The Sinjar Resistance Units) を表している (2015年3月) ©林典子
硫酸をかけられた被害者女性と一緒に生活
私は2010年にパキスタンで結婚や交際を断った結果、または家庭内暴力の延長で、男性から硫酸をかけられた被害者の女性たちの取材をしました。当時、被害者の数は毎年150から300人とされ、その半数以上は11歳から20歳の少女たちと報告されていました。地方の村では、被害者に裁判で争う費用がないなどの理由で、訴えが認められるケースもごく僅かでした。
被害者の女性たちと一緒に生活をしながら彼女たちの日常を追ったのですが、こうした硫酸の被害者を取材したパキスタンの村々は、私が訪れたイラク北部以上に、一般的には保守的または閉鎖的といわれるコミュニティだったと思います。女性たちは全身を覆うブルカを着用し、女性は男性が一緒でないと村の中を歩き回ることは基本的にはありませんでした。だからと言って取材が大変だったという感覚はありません。
 夫に硫酸を浴びせられた22歳のセイダ(左)。実家にセイダの様子を確かめにきた看護師のベルキースと(2010年8月)©林典子
夫に硫酸を浴びせられた22歳のセイダ(左)。実家にセイダの様子を確かめにきた看護師のベルキースと(2010年8月)©林典子
地元の住民が安全を気にかけてくれた
パキスタンでは、私が女性だということで、現地の家庭で寝泊まりをしながら撮影や取材をすることが当たり前に可能になったこともありました。逆に女性だということで物理的に入ることのできない空間もありましたが。
矛盾しているように聞こえるかもしれないですが、硫酸を女性に浴びせ、名誉殺人が起きるような地域であっても、男性たちの多くは本当にあたたかく、外国から来た私の安全を常に気にしてくれました。硫酸の被害者の女性たちを支援していた多くは、男性の医師や弁護士、活動家たちでした。
情報共有できる場所を取材拠点として安全を確保
ヤズディの取材を振り返っても、特に戸惑ったことはありません。イラクには、私と同世代の海外の女性のジャーナリストや写真家が当たり前のように活動していました。
私は現地に行くたびに、彼女らが拠点にしている家に数日間滞在して、治安を含めた情報を共有してから地方の町へ取材に出かけるようにしていました。治安が不安定な場所での取材に、それなりのリスクがあるのは男性も女性も同じです。安全が100%保障されている取材など世界中どこに行ってもありません。
大変だったこととしてあげるとしたら、イラクは食事が合わないこと、パキスタンは45度を超える猛暑の中で歩き回って撮影を続けたことでした。衛生状態が悪い現場もありました。取材が進まず数週間写真を撮らずに、様子をうかがうだけの時間もありました。取材以前に、通訳としっくりといかず、信頼関係を築くのにエネルギーを費やしたりしたこともあります。しかし、こういったことはどんな取材にも付きものだと思っていますし、その時大変だったと思っても、数年経って振り返れば、たいしたことではありませんでした。
たくさんの悲しみなども取材してこられたと思います。写真家の道を選ばなければよかったと思った瞬間などもありましたか? もちろん、この仕事を続けていて良かったと思える点についても聞かせてください。
海外の取材から戻った日本で感じたストレス
取材をした方々の中には、理不尽な境遇の中で生きてきた方々も多くいましたし、そういった方々に直接向き合う中で、私自身も取材中に感情的になった経験は何度かありました。ただ、それが理由でこの道を選ばなければよかったと思ったことはありません。私以上に現場で大変な経験をされている写真家の方々はたくさんいらっしゃると思います。
私の場合は海外の取材現場から離れ、発表活動をする中でストレスを感じたことの方が多くありました。日本で活動をすることの方が大変だったと感じています。作品を発表する過程の中で、私が女性であるということを必要以上に象徴する形でメディアを通して私と作品が関連づけられ発表されたことについては違和感がありました。海外の媒体で作品を発表するときには、感じたことのないストレスでした。
イラク取材に関しては、「自己責任論」と関連づけた批判もありました。私が女性であるということが理由でイラクのような現場に行くことに対して、危機管理を怠っているかのような先入観から、「危なっかしい」と言う方も多くいました。取材をしてきた内容を伝えるためにテレビなどに出演すれば、服装や髪型など外見的な面からSNSなどで批判をされることもありました。日本で発表活動をする過程では、どのようにメディアやSNSと関わるかということについて、より慎重になったと思います。
だからと言って、この道を選ばなければよかったとまでは思いません。
仕事とは感じずチャレンジできる幸せ
この仕事を続けてきて良かったと思う点ですが、フリーランスという立場もありますが、私自身のプロジェクトに関しては「仕事」だとは思わずに、私自身のペースで、誰からもプレッシャーをかけられずに、取材を続けてくることができたことです。これまでさまざまな立場や経験を持った方々と出会うことも多く、刺激を受けることもありました。続けることは大変ですが、写真家として新しいことにもチャレンジしたいという思いもあり、そう思えることはどんな職種であっても幸せなことだと思います。
 夫をISの戦闘員に殺害された19歳のズィーナ。 ビワ(クルド語で「家がない」という意味)と名付けた子供に母乳を与える(2015年6月)©林典子
夫をISの戦闘員に殺害された19歳のズィーナ。 ビワ(クルド語で「家がない」という意味)と名付けた子供に母乳を与える(2015年6月)©林典子
 10ヶ月の息子をゆりかごに乗せてあやすズィーナの義母(2015年6月)©林典子
10ヶ月の息子をゆりかごに乗せてあやすズィーナの義母(2015年6月)©林典子
北朝鮮の「日本人妻」取材
北朝鮮の「日本人妻」の取材をこの数年力を入れていらっしゃいますね。このテーマについて取材しようと決めた理由などについてお話しいただけますか。
時代と政治に翻弄された日本人女性たちの存在
1959年から始まった在日朝鮮人らの帰国事業では、日本で在日朝鮮人と結婚をした約1800人の日本人女性が、夫と共に朝鮮民主主義人民共和国に渡りました。1910年から45年まで朝鮮半島は日本の植民地でした。日本人妻と呼ばれる女性たちが結婚した朝鮮人の男性たちは、その時期に日本に自主的に渡ったか、労働徴用や徴兵などの戦時動員として連れてこられた在日1世、またはその子供として生まれた2世です。
帰国事業が行われた1950年代、在日朝鮮人の多くは民族差別や職業差別に苦しみ、失業率は日本人の約8倍でした。そのような現実に直面し、日本での将来に希望を見出せずにいた多くの在日朝鮮人やその家族は、北朝鮮への移住を決断したのです。日本人妻たちも数年で里帰りができると信じ、海を渡りました。しかし、緊迫した日朝関係が理由で日本人妻たちの多くは里帰りが叶いませんでした。97年から2000年の間に赤十字が主導して行われた里帰り事業で、わずか43人が数日間故郷を訪問できただけです。彼女たちが新潟港を出港してから半世紀以上が経ち、今も現地で暮らす日本人女性の個人の存在が伝わることは、これまでほとんどありませんでした。
年齢的にも高齢であるはずの女性たちの生きてきた証を残したいと思い、2013年に初めて訪朝をしました。それ以降、北朝鮮で暮らす8人の日本人妻の方々の取材を重ねながら、彼女たちの日本各地の故郷も訪れ、複雑な関係にある日朝間を行き交う個々の記憶を辿るような取材をしています。
これまで12回訪朝をしましたが、現在はコロナの影響で現地での取材ができません。その間、日本で出来る情報収集や取材を深めていきたいと思っています。写真家として活動を始めて以降、日本人妻のテーマが一番長い取材になっています。今は写真集の準備も進めています。
 1961年に朝鮮民主主義人民共和国への渡航直前に夫と撮影した記念写真を手にする、日本人妻の井手多喜子さん(2016年8月、北朝鮮元山市で)©林典子
1961年に朝鮮民主主義人民共和国への渡航直前に夫と撮影した記念写真を手にする、日本人妻の井手多喜子さん(2016年8月、北朝鮮元山市で)©林典子
コロナ禍のなかでの発表の場
2016年の「ヤズディの祈り」の写真展開催中に、とある男性から、「ボンヘイさんは元気ですか」との質問を受け、その数か月前に亡くなったことを伝えると、その男性が涙ぐまれた、と著書「フォトジャーナリストの視点」(雷鳥社)で読みました。
写真展開催は写真家にとって貴重な交流の場です。コロナ禍のなか、発表の場の確保をどのようにしようと考えられていますか?
発表できるタイミングで発表する
私はそもそも発表の場をできるだけ多くの場所でしたいと思って活動をしてきたわけではありませんでした。取材しているプロジェクトの進捗状況を考えながら、発表できるタイミングが来たときに発表をするなど、マイペースに進めてきたという実感があります。本当に発表をしたいと思った時に、何らかの手段を使って発表をすればよいのではないかと思います。
さまざまな紙媒体が廃刊したり、写真展会場なども限られたりしている状況ではありますが、今は以前よりも個人がさまざまなツールを使って発信するという傾向も増えてきています。大手メディアや、大きな展示会場だけが発表の場であるという認識も、若い世代の写真家たちの中では少なくなってきているという印象も受けています。
 窓から見える朝鮮民主主義人民共和国、東部の元山市内の風景(2018年11月)©林典子
窓から見える朝鮮民主主義人民共和国、東部の元山市内の風景(2018年11月)©林典子
取材テーマの選定について
幅広い分野の中から、どのように一つのプロジェクトとして取り組もうとするテーマや対象を決められていますか?
関心を持ち続けられるテーマを
一番大切なことは写真家自身が向き合っているテーマに関心を持てているかということだと思います。少し興味を持ったら、調べたり取材を初めて見たりして、それで関心が薄れてきたら離れてみるということもありだと思います。一つのテーマを長期的に取材するということは、相当なエネルギーや時間も使います。自分自身が追求していきたいと自覚しながら進められるプロジェクトであるということが大切だと思います。
ドキュメンタリーフォトグラファーを目指す若い世代に向けて
若い世代が大手メディアや写真集、雑誌などの印刷メディアからの情報収集よりも、SNSからの情報収集を重視する傾向がここ数年顕著です。ドキュメンタリーフォトグラファーが今後、特に若い世代へ向けて、どのような内容や伝え方をするのが良いとお考えですか?
「狭い層に向けて深く」も、伝え方の一つ
私がどうこう言える立場にはありませんが、個人的にはそれぞれが伝え方を模索しながら考えていけばいいのではないかと思います。
ドキュメンタリー写真家の中にはそれぞれがプロジェクトの内容によって、その都度発表手段を変えている方も多くいると思います。取材したテーマによっては大手メディアを通して大衆に向けて伝えるという方法もあるかもしれませんし、逆にあえて狭い層にそれでも深く伝えたいと、作品性にこだわって活動をされている方もいると思います。どちらが良いということではなく、その時その時の自身の取材の方法や表現の可能性を模索し、伝えたい方法も考えたら良いのではないかと思います。
遠い世界の出来事も一瞬に「日常化」する今だから
今は紛争地に生きる市民または遠い国の小さな集落で暮らす人々が、自身の日常を撮影した写真や動画を発信することができ、それらがリアルタイムで日本に暮らす私たちの携帯電話やパソコンの画面を通して表示されるような時代になりました。物理的には触れることのない遠い世界の出来事であっても、画面を通すことで独特な距離感を保ちながらも一瞬にして「日常化」しているような印象も受けます。
そのような時代だからこそ、社会の流れに合わせて伝える内容や表現の方法を模索するということではなく、写真家やフォトジャーナリストたちは、個人の感覚や独自の視点を持ってプロジェクトに向き合い、どう伝えてのこしていきたいかということを、私自身もそうですが、自問しながら活動していくことが大切なのではないかなと思います。
 シンガル山麓のカナソール村に暮らしていたヤズディ女性が、1978年に結婚した直後に購入したミシン。2014年8月にISの攻撃によって村が奪還されたが、長年愛用していたこのミシンをイラク国内の避難先に運んできた(2016年7月)©林典子
シンガル山麓のカナソール村に暮らしていたヤズディ女性が、1978年に結婚した直後に購入したミシン。2014年8月にISの攻撃によって村が奪還されたが、長年愛用していたこのミシンをイラク国内の避難先に運んできた(2016年7月)©林典子

林 典子さん
1983年、神奈川県生まれ。イギリスのPhoto Agency 「Panos Pictures」所属。国際紛争学・平和構築学を専攻していた、大学時代にガンビア共和国の地元新聞社で写真を撮りはじめる。卒業後は、フリーランスの写真家として国内外で活動。第7 回名取洋之助写真賞、仏「ビザ・プール・リマージュ」金賞、全米報道写真家協会賞1 位など受賞。著書に「キルギスの誘拐結婚」(日経ナショナル ジオグラフィック社)、「ヤズディの祈り」(赤々舎)、「フォト・ドキュメンタリー 朝鮮に渡った日本人妻 60年の記憶」(岩波新書)など。英GRANTA誌、ニューヨークタイムズ紙、独Stern誌、英ガーディアン誌、National Geographic誌などに写真や記事を寄稿
